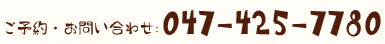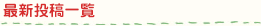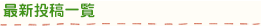- 2020年06月06日
- くすのきカイロプラクティックオフィス
- 整体の考え方肩の症状
COVID-19への措置として社会的にリモートワークの推奨が叫ばれましたが、その結果肩・首・背中・腰にコリの症状や痛みにまで発展した人が少なくないように思います。
元々、職場でもノートPCではあったと思いますが自宅では机や椅子が仕事用にはなっておらず食卓で仕事をしたり床に座って仕事、ひどいケースではベッドの上で仕事をしていたという話も聞きました。
職場でノートPCを使っていても肩や首、背中に負担が掛かるのに自宅の環境だとさらに拍車が掛かってしまいます。
今後はリモートワークも一般的になって行くでしょうからデスクと椅子を買ってという人もいるかもしれませんが、日本の住宅事情を考えた時にそんなスペースがあるのか?
という疑問も出て来ます。
その前に仕事用のデスクや椅子を揃えたところでノートPC自体がコリを助長させやすい代物だという事も言えます。
出来ればデスクトップを使いたい。
デスクトップなら目線も水平に保てるのでずっと下を向き続ける事はない。
モニターを覗き込む事と肩をすくめる事を注意すればコリはそこまでひどくは出ません。
でも今更デスクトップなんて置けるわけもない。
で、あればノートPCで同じ状況を作ってあげればいいと言えます。
今はこのようなノートPC用の台が売っています。

ここにノートPCを置けばいいのです。
でも、そうするとキーボードを打つのに腕がずいぶん上がってしまいその状態が続くと肩こりや背中のコリが出て来てしまいます。
そこで使いたいのがBluetoothで接続するキーボードです。

これなら目線は水平を保て、腕も下げられます。
有線のようにサクサク打てない場合もありますが、少なくてもそのままひどい姿勢で長時間仕事をするよりははるかに体へ対する負担は軽くなると思います。
肩や首のコリを我慢していると頭痛が出たり、腕が痺れたりという二次的な症状を引き起こします。
そうなると深部のコリを取り除くしか改善方法は無くなってしまいます。
そうならないように日々の姿勢には気をつけて仕事をして行きましょう。